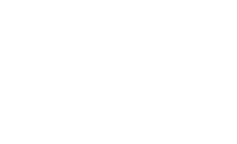※本記事のリンクには広告が含まれます。
「最近、プログラミング教育ってよく聞くけど、うちの子どもにやらせたほうがいいの?」
「子どもがプログラミングに興味をもっているけど、何から初めていいかわからない」
「プログラミングの教育ってきっと難しいんでしょう?」
そんな悩みを持っている親御さんは多いと思います。近年、ITのすさまじい発展から、世界的にプログラミングへの関心が急速に高まっています。子どもの将来を心配する保護者の方は「うちの子にもプログラミングを学ばせた方が良いのだろうか?」と考える機会が増えているのではないでしょうか。
この記事では、プログラミング初心者ながら小学2年生の息子と一緒にプログラミングを学んできた筆者が、小学生がプログラミングを学習していくうえでおすすめの学習方法をお伝えしていきます。
プログラミングに興味のあるお子さんが、どのようなプロセスでプログラミングのスキルを向上させていけばよいかを解説していきます。これからプログラミングを学んでいきたい親子にぜひ役立ててもらえれば嬉しいです。
目次
結論:小学生がプログラミングを始めるための手順

結論から言うと、小学生がプログラミング学習をすることは簡単で、おすすめです。論理的思考力や問題解決能力の育成に役立ち、将来プログラマーにならずとも社会で生きていく力をつけることができるからです。
小学生のお子さんがプログラミングのスキルを学習していく手順は以下のステップになります。
- ステップ1:ネット環境と端末(パソコンかタブレット)を準備する
- ステップ2:無料のプログラミングツール(Scratchなど)で遊んでみる
- ステップ3:自分で簡単なアプリを完成させる
- ステップ4:プログラミングスキルを伸ばす。
- ※お子さんに応じてプログラミングスクール・通信教材を活用する
以上のステップで、小学生でもプログラミングスキルを高めていくことができます。
小学生にプログラミング学習をおすすめする理由
論理的思考力や問題解決能力の育成
プログラミングは、論理的思考力や問題解決能力を育む上で非常に有効な手段です。日本では、2020年から小学校でプログラミング教育が必修化されました。文部科学省の「小学校プログラミングの手引」において、以下の文が記述されています。

中央教育審議会の議論では、 情報化の進展により社会や人々の生活が大きく変化し、将来の予測が難しい 社会においては、情報や情報技術を主体的に活用していく力や、情報技術を 手段として活用していく力が重要であると指摘されています。さらに、子供 たちが将来どのような職業に就くとしても、「プログラミング的思考」など を育んでいくことが必要であり、そのため、小・中・高等学校を通じて、プ ログラミング教育の実施を、子供たちの発達の段階に応じて位置付けていく ことが求められると指摘しています。(中略)
そして、「プログラミング的思考」とは、「自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組合せが必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記号の組合せをどのように改善していけば、より意図した活動に近づ くのか、といったことを論理的に考えていく力」であると説明されています。
引用:文部科学省「小学校プログラミングの手引」
簡単にいうと、子どもたちがこの先どんな職業につくにしても
「やりたいことことのために」「どうすればよいか順番に考え」「もっとよくするにはどうすればよいか考える」
ためにプログラミング教育が重要ということです。プログラミングといえば、「ゲーム」「Webデザイン」「AI」などのイメージをもつ人が多いと思いますが、プログラミングは「どうしてそうなるのかな?」「どうしたらうまくいくかな?」を考える力をつける効果があります。学校で習う算数や理科のような学習はもちろん、社会に出たあとの「生きる力」にも十分生きてきます。
また、IT技術が急速に進化する現代社会において、プログラミングスキルは将来の選択肢を広げる可能性を秘めています。情報を処理する力や、コンピュータを動かすことができるスキルは今後生かされるのは間違い有りません。
学校だけではプログラミングは習得は難しい
日本では、2020年から小学校でプログラミング教育が必修化されました。一方で、最も大きな課題の一つは、プログラミングを教える教員の知識や指導力の不足でがあげられています。多くの学校教職員は、自身がプログラミング教育を受けていない世代であり、十分な知識を持っていないために、指導に不安を感じている現状があるようです。

プログラミング教育が必修化されたといっても、これまでも多忙とされていた学校が、新たに導入された「プログラミング学習」にすぐに対応していくのは難しいでしょう。
お子さんが「プログラミング」を学び、「プログラミング的思考」を十分に発揮していくには、学校だけでなく、学校以外で自分からプログラミングに取り組む必要があります。
しかし、「プログラミング」と一口に言っても、その世界は奥深く、何から始めたら良いのか迷ってしまう方も多いでしょう。そこで小学生がプログラミングを始めるにあたって、目的の設定からおすすめの学習方法、教材、端末まで、幅広く解説していきます。
小学生でもプログラミングは簡単にできる。
この記事を読んでいる読者の中には、「プログラミングなんてうちの子には無理だよ」、と思う方もいると思います。確かに、プログラミング自体は非常に奥が深く、一朝一夕にできるものではありません。
しかし現在は無料の子ども向けプログラミング学習ツールがたくさん公開されています。子ども向けプログラミング学習ツールの中には、「ビジュアルプログラミング」といって、ドラッグ&ドロップを使い視覚的・直感的にプログラミングをすることができるものがあります。ビジュアルプログラミングでは、文字やタイピングが未習得の小学生低学年でも、プログラミングの考え方を学ぶことができます。
難しいと身構えずに、気軽にプログラミングの世界に足を踏み入れることができる時代です。
ステップ1【準備】パソコンとインターネット環境を用意しよう
ここからは、小学生低学年がイチからプログラミングをするための手順を、順を追って説明していきます。
インターネット環境を用意する。
まず、インターネットができる環境を用意しましょう。無料の子ども向けプログラミング学習ツールはブラウザ上で行うものが多く、インターネット通信が必須になります。また、プログラミングでは「うまくいかない」ことが多発するので原因を調べるためにインターネットを使用します。

自宅にインターネットの固定回線がすでにある方はそのままのネット回線で問題ありません。
固定回線が自宅にない方は、保護者のスマホのデザリングをするという手段もあります。プログラミング学習初期には、そこまで大容量の通信をせずに学習をすすめることが可能です。しばらくはデザリングでやってみて、「オンラインスクールを受講する」「多く調べ物をする」「画像を多くダウンロードする」など、本格的に通信をするようになったら、ご自宅に固定のインターネット回線を契約しましょう。
プログラミングをするためのパソコンかタブレットを用意する。

たまに、「プログラミング教室でしかパソコンを触らない」というお子さんがいらっしゃいますが、教室で触るだけだとなかなかプログラミング的思考はなかなか身につきません。
インターネット環境と同じく重要なのが、お子さん自身がプログラミングをするための端末になります。「端末」とは、パソコンやタブレットのような実際にプログラミングをするため操作をするための機器のことです。
プログラミングを身につけたいなら、お子さんが好きなときに触ることができる端末(パソコンorタブレット)を用意することをおすすめします。なぜなら、プログラミングを身につけるためには気の済むまで熱中したり、わからないことが解決するまで調べることが求められます。自宅で好きなときに触ることができるパソコンかタブレットは必須になってきます。
プログラミング用の端末を用意する方法
・お子さん用のパソコンかタブレットを購入する。
・親のパソコンを共有する。
・小学校で配布されているパソコンを使う。
プログラミング用の端末を用意する方法は、上記のどれでも大丈夫ですが、いずれも「インターネットにつなぐことができる」「お子さんが触りたいときに触ることができる」ことが重要です。最初は保護者の使っているパソコンを共有してあげながら始めるのも問題はないです。
また、最近は小学校で児童1人に1台ICT端末が配布されることが多いと思いますので、学校のタブレットが自宅で自由に使えるなら、学校の端末をプログラミング学習に使ってもいいでしょう。(自宅での使い方のルールは学校のルールに則ってください)
プログラミングにiPadはありだが、長期的にはパソコンがほしい。
「iPadならあるんだけど、パソコンを買ったほうがいいの?」というご家庭もいるかと思います。
筆者の回答は
「iPadでもプログラミングはできるけど、用意できるならパソコンでやってほしい」ということになります。
iPadよりもパソコンの方が、プログラミングを続けるなら将来性があります。
しかし、簡単なプログラミングならiPadでもできます。すでにiPadを持っていて、新しくパソコンを買うのをためらう人は、iPadで初めてみるのもよいでしょう。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| iPad | ・子どもが操作に慣れている。 ・持ち運びがしやすく ・iPad専用のプログラミングアプリがる | ・汎用性が低く、使えないアプリ・言語も多い ・消費コンテンツで遊んでしまう ・タイピングスキルが身につきにくい |
| パソコン | ・汎用性が高く、ほとんどのプログラミングに対応している ・子供用プログラミングだけでなく、本格的なプログラミングに発展していきやすい。 | ・パソコンがない家庭が多く、購入費がかかる。 ・タブレットでしか開かないアプリもある。 |
プログラミングを始める際のおすすめのパソコン
上記で述べたように、長期的にはお子さん用のパソコンを買うほうが良いです。パソコン選びも悩んでしまうこともありますよね。
お子さん用のパソコンの選び方ですが、小学生がScratchなどをやることだけなら、そこまで高いスペックでなくてもよいです。メモリは8GB程度、ストレージも256GB程度あれば十分です。
大事なことは、お子さんが「いつでも触れる」「使いやすい」ことです。高額なパソコンを用意する必要はありませんが、ブラウザでゲームが動かせたり、プログラミングに必要な画像を保存して置けるくらいのスペックはあるほうがよいでしょう。
ちなみに筆者は、パソコン選びが苦手な人には、MacbookAir(M2以上)をおすすめしています。
| 【新品/未開封/1年保証】 Apple MacBook Air MLY33J/A 13.6型 M2チップ SSD 256GB メモリ8GB 8コア ミッドナイト MLY33JA Liquid Retina ディスプレイ 新品 未開封価格:133980円 (2025/4/2 22:01時点) 感想(8件) |

子どもにMacbookを与えるのは贅沢すぎるように感じますが、最低限の設定をすれば動かせるので、パソコン初心者にとっては始めやすいパソコンです!
ステップ2:子供用プログラミング学習ツールに取り組む
インターネット環境とパソコン(タブレット)が用意できたら、さっそくプログラミングを始めてみましょう。
「急にプログラミングなんて無理・・・」と身構える必要はありません。非常に簡単に始めることができますよ。
子ども向けプログラミング学習ツールに登録する
まずやることは、子供向けのプログラミング学習ツールにアクセスし、プログラミングに挑戦しましょう。現在、筆者がおすすめしているのは「Scratch(スクラッチ)」です。
小学生におすすめの、無料の子ども向けプログラミング学習ツール
以下では、自宅でお子さんが取り組める無料の子ども向けプログラミング学習ツールを紹介していきます。いずれも初心者用のチュートリアルがあり、初めてプログラミングをするお子さんでも順を追って取り組むことができます。

筆者のおすすめは断然Scratch(スクラッチ)です!
| イメージ画像 | 無料プログラミングツール | 特徴 |
|---|---|---|
 |
Scratch (スクラッチ) | ・ブロックを組み合わせてプログラミングができる。 ・豊富なチュートリアルと日本語対応。 ・他の人の作品を共有し、改造できる。 ・ブラウザで無料利用可能。 |
 |
Hour of Code (アワーオブコード) | ・「1時間でできる」アプリ開発。 ・プログラムを段階的に学習できる。 ・日本語対応の教材も多数あり。 ・ブラウザで無料利用可能。 |
| VisCuit(ビスケット) | ・文字ではなく自分の絵でプログラミング ・「メガネ」という仕組みで楽しく学ぶ。 ・単純な仕組みで簡単に楽しめる。 ・ブラウザで無料利用可能 |
|
 |
マインクラフト(教育版) ※英語サイト | ・マイクラの世界観でプログラミングを学べる ・ブラウザではなくパソコンにインストールして遊ぶ。 ・教育現場用にリリースされた。現在は個人利用も可能。Microsoft365の登録が必要。 ・基本的に有料だが、一部体験版ワールドが存在 |
ステップ3:プログラムをひとつ完成させる。
子供用のプログラミング学習ツールを少し遊ぶことができたら、なにかひとつ、プログラムを完成させることを目標にとりくんでましょう。
アプリを完成させる、といっても決して難しくは有りません。無料の子ども向けプログラミング学習ツールの多くはチュートリアルがついていて、順を追って簡単にプログラミングを行うことができます。
重要なのは、最後まで完成させることです。
自分の行ったプログラミングが形となり、動かすことができた達成感が、次のプログラムへの創作意欲を膨らませます。

はじめは「簡単すぎる」と親が思ってしまうくらい簡単なものから取り組んで自信をつけていきましょう!
子どものやる気を維持するには、保護者も一緒にプログラミングをする
保護者がプログラミング初心者ならば、お子さんとともに、保護者もプログラミングをことをおすすめします。親御さん自身がプログラミングに取り組むことで、「どうしたらうまくいくのか」「なぜうまくいかないのか」を、親子で一緒に考えるようになるからです。
プログラミングは、失敗と改善の繰り返しです。うまくいかないときに「なぜできないんだろう?」「何が悪いんだろう」を考え続けることがプログラミングでもっとも重要なことです。
親御さんが一緒に子どもと「考え」たり「失敗」したりすることで、お子さんは「プログラミングにおいて失敗するのは当たり前のことなんだ」と自覚することにつながります。
失敗したとき、親御さんが「試行錯誤したり」「グーグルで検索したり」する様子もぜひ見せてあげましょう。低学年のお子さんがプログラミングを学習する際に、親子でともにプログラミングを学んでいくことが重要なことです。
ステップ4:プログラミング力を伸ばす

プログラミングができる環境を整えて、子ども向けプログラミング学習ツールのチュートリアルをクリアできたなら、プログラミング学習のスタートとして十分です。
プログラミング力を伸ばす段階では、以下のような活動を繰り返します。
- 覚えたプログラミング学習ツール(Scratchなど)でちがうアプリをつくる
- 2つ目の言語を覚える(Scratchの次にマインクラフトをやってみるなど)
- 自分で調べたり、試行錯誤しながら、複雑なプログラムを作る。
プログラミング力が伸びてきて、いくつかアプリができてきたら、。つくったアプリを家族や友達に遊んでもらい、感想をもらうことで、お子さんはプログラミングでアプリを完成させることの達成感を強く味わうことができます。また、改善点を指摘してもらうことで、「どうしたら、よりうまくいくのか」と深く考え、プログラミング力の向上につながります。
伸び悩んでしまったら、プログラミング教室や通信教材を検討しよう

プログラミング学習をすすめていくうちに、何度も「困ったこと」「うまくいかないこと」に直面します。どうしても解決できない場合は、プログラミング教室や通信教材を検討しましょう。
あとはお子さんがやりたいことや、できることにどんどん取り組み、お子さんのプログラミング力を伸ばしていく段階になります。
プログラミング教室や通信教育では、プログラミングスキルを修得することを体系化してまとめてくれていますので、効率よくプログラミングスキルを会得することができます。
プログラミング教室のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・ 仲間と一緒に学べる環境がある ・質問がすぐにできる ・専門家から直接指導が受けられる ・学習環境が整っている ・モチベーションを保ちやすい |
・ 月謝などの費用がかかる ・送迎の時間が必要 ・決められた時間に通わなければならない ・教室の場所や時間帯が限られる ・進度が周囲に合わせられてしまう |
小学生がプログラミング教室を選ぶ際に重要なポイント5つ

ひとくちに「プログラミング教室」といっても、特徴はさまざまです。使っている教材、学習の進め方、価格、指導者のスタンスなどです。プログラミング教室を選ぶ際には、以下のポイントを意識して選ぶとよいでしょう。
小学生におすすめのプログラミング教室5選
プログラミング教室はたくさんありますが、ここではなるべく全国的に展開されている大手のプログラミング教室を5つ紹介します。
これ以外にも住んでいる地域にあるプログラミング教室でも大丈夫です!その際は、前述した「プログラミング教室を選ぶ際に重要なポイント5つ」を確認ください!
おすすめのプログラミング教室
| 教室名 | 特徴 |
|---|---|
| QUREO(キュレオ)プログラミング教室 | サイバーエージェントグループが開発した小学生向けカリキュラムを採用。ゲーム作成を通じてプログラミングの基礎を学ぶ。全国47都道府県に2,500以上の教室を展開し、教室数国内No.1。 |
| エジソンアカデミー | 学校教材メーカーのアーテックが開発したロボット教材を使用。毎月1体のロボットを組み立て、プログラミングを学ぶ。全国45都道府県に約900教室を展開。 |
| LITALICOワンダー | 子ども一人ひとりに合わせたオーダーメイドカリキュラムを提供。ゲーム&アプリプログラミング、ロボット製作、デジタルファブリケーションなど多彩なコースを用意。東京、神奈川、埼玉に教室を展開し、オンライン受講も可能。 |
| ヒューマンアカデミー こどもプログラミング教室 | 総合教育機関ヒューマンアカデミーが運営。Scratchやマインクラフトを使用した実践的なカリキュラムで、プログラミング的思考や課題解決力を育成。全国に200以上の教室を展開。 |
| スタープログラミングスクール | 小学生・中学生向けに、ゲーム制作やロボットプログラミングなど多彩なコースを提供。関東、中部、関西、九州エリアに教室を展開。 |
プログラミング通信教材で自習で学習する。
「高額な塾に通わせるのは家計が厳しい」「プログラミングはマイペースに取り組ませたい」「教室への送迎の時間がない」というご家庭には、プログラミング通信教材を検討してみましょう。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 自分のペースで学習できる。 時間や場所を選ばない。 プログラミング教室よりも安価にできる。 | 自己管理が必要で、モチベーション維持が難しい。 質問への回答に時間がかかる 教材の選択肢が少ない |
Z会プログラミングコース
プログラミング通信教材の有名な教材の一つが、「Z会プログラミングコース」です。通信教材大手の「Z会」が行うプログラミングに特化したコースであり、オリジナル教材で「プログラミングの思考」を学習できます。
オリジナルの教材で、動画をふまえながら丁寧に順を追って教えてくれ、小学生低学年のお子さんでも一人でプログラミングに取り組むことができます。プログラミング教室への送迎が難しかったり、家でお子さんと一緒に学習に取り組むことが難しい保護者の方には有力な選択肢になります。マイペースに取り組むことができ、プログラミング教室と
また、教材費は月額4000円程度で、プログラミング教室の月謝の平均の半額程度でプログラミング学習ができるのも魅力のひとつです。
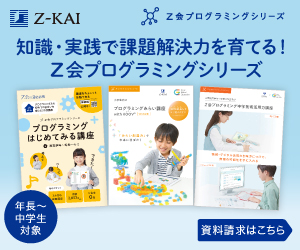
まとめ
ここまで読んでいただいてありがとうございました。小学生でも、今は簡単にプログラミングを始めることができる時代です。お子さんがプログラミングスキルを伸ばし、未来につながる力をつけていくことを願っています。